「国語ができる人は頭がいい」とよく言われますが、それは本当なのでしょうか?
実は国語力と頭の良さには密接な関係があります。
国語力が高い子どもほど、思考力や判断力、そして他者とのコミュニケーション能力も高い傾向にあります。
一方で、国語力がないとどうなるのでしょうか?
読解力不足から、他の教科の成績が振るわないことが少なくありません。
また、将来的に対人関係で苦労するかもしれません。
そうならないためにも、小学生の時期から国語力を伸ばすための対策を取りましょう!
この記事では、以下について解説します。
- 「国語ができる人は頭がいい」と言われる理由
- 国語力がないとどうなるか、将来への影響
- 小学生の国語力を伸ばす方法
- 小学生向け国語力を伸ばすおすすめ本
国語力を伸ばすのに効果的な本の読み方など、家庭で取り組めるおすすめの方法も紹介しています。
お子さんの頭の良さを伸ばしたい人は記事を読み進めてくださいね。
「国語ができる人は頭がいい」のは本当?国語力と頭の良さの関係
まずは「頭の良さ」と「国語力」について、それぞれの定義を明確にしましょう。
「頭の良さ」とは?認知能力と非認知能力の両方が大切
「頭の良さ」と聞くと、テストの点が高い子を思い浮かべるかもしれません。
しかし本当の意味での「頭の良さ」は、認知能力と非認知能力の両方から成り立っています。
○認知能力について
これは学業成績や偏差値といった形で可視化される能力で、情報や知識をどう扱うかに関わる力です。
- 記憶力
- 計算力
- 読解力
- 理解力
- 言語能力
- 論理的思考力 など
○非認知能力について
数字では測りにくいものの、充実した人生を歩むために欠かせない力を指します。
- コミュニケーション能力
- 他者と良好な関係を築く
- 共感力
- 忍耐力
- 自制心
- 目標に向かって努力する力
- 想像力
- 洞察力
- 創造性
- 自己肯定感
- 自己コントロール力 など
頭がいい人とは、認知能力と非認知能力の両方がバランスよく高い状態の人なのです。
「国語ができる人は頭がいい」と言われる理由
○国語ができる(国語力が高い)とは
国語力とは、単に漢字が書けることや文法を理解していることだけではありません。
国語力には以下の力が含まれています。
- 分析力/論理的思考力/読解力:読んだ内容や聞いた内容を正確に把握する力
- 感受性や感性の豊かさ:他者の気持ちを感じ取ったり文学作品に感動したりする力
- 想像力:自分が経験したことのない事を思い描く力
- 表現力:自分の気持ちや考えを正確に伝える力
- 語彙力:漢字やことわざ、慣用句などを含む
- 教養
これらの力が総合的に高い状態が「国語ができる」ということです。
○国語力と頭の良さの関係
「国語ができる人は頭がいい」理由は、国語力が認知能力および非認知能力を育てる土台となるからです。
まず、認知能力との関係を見てみましょう。
「国語力が高い」ということは、認知能力である「語彙力」「理解力」「論理的思考力」が高いということに他なりません。
次に、非認知能力との関係です。
国語力が高いと、適切に自分の気持ちを伝えることができるので、「他者と良好な関係を築く」ことに繋がります。
また、想像力を働かせて読書をすることで、「共感力」や「洞察力」も育ちます。
このように、国語力は頭の良さを形成する能力の基礎となるのです。
国語力がないとどうなる?将来への影響
国語力が低いと、学校生活だけでなく将来の社会生活にも大きな影響があります。
○どの教科の成績も伸び悩む
読解力や論理的思考力不足のため、書かれている内容や筆者の主張を自己中心的に解釈してしまいます。
算数では文章題が解けず、理科では実験の手順や結果の考察が理解できません。
社会では資料を読み取れず、歴史の因果関係も把握できません。
国語力はすべての学習の基盤ですから、学年が上がるにつれて全教科で学習についていけなくなります。
○適切なコミュニケーションが取れない
語彙力が低いため、限られた言葉で全てを表現しようとします。
また、微妙な気持ちの違いや状況の説明ができず、曖昧な表現が多くなります。
相手の言葉の真意を理解できないこともあるので、誤解が生じやすくなるでしょう。
社会に出てからも、コミュニケーション不全による人間関係のトラブルに悩まされる恐れがあります。
○問題が発生したときに解決への糸口を見つけられない
国語力が不足していると、深い思考や論理的な考えが苦手な傾向があります。
そのため、表面的な理解しかできず、「なぜそうなるのか」という本質的な理解に到達できません。
これは学習だけでなく、日常生活での問題解決能力にも影響します。
○健全な人間関係を築くのが難しい
国語力である「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」が不足した状態では、自分や相手の置かれている状況を把握することや、相手の気持ちを想像し配慮すること、自分の伝えたいことを正確に表現することが難しく、健全な人間関係を築くのに大きな支障が出ることに繋がります。
国語力がないとどうなるかを考えることは、子どもの将来を見つめることでもあります。
小学生の国語力を伸ばす方法|家庭で取り組めること
国語力は日々の習慣で育てられる力です。
小学生の時期に正しいアプローチで国語力を育てれば、お子さんの将来の可能性が大きく広がります。
文部科学省では、本の読み聞かせや家庭内のコミュニケーションの重要性を強調し、コミュニケーションを増やす努力が子供たちの国語力を育てることに直結する、と述べています。
上記を踏まえて、子どもの国語力を高めるために家庭でできることを見ていきましょう。
語彙力を鍛えることから始めよう
○語彙力を鍛える大切さ
語彙力は国語力の土台です。
言葉を多く知っているほど、細かいニュアンスや複雑な概念を理解でき、自分の考えを正確に表現できるようになります。
○語彙力を高める具体的な方法
・日常会話で意識的に多様な言葉を使う(「きれい」だけでなく「美しい」「華やか」「優雅」など)
・読み聞かせや読書、音読を行い、分からない言葉があれば辞書で調べる
・家族で言葉遊びをする(しりとり/ことわざクイズ/慣用句カルタなど)
・子どもが「すごい」などの曖昧な表現を使ったときは、「どんなふうにすごかったの?」と具体的に言い換えさせる
・漢字の成り立ちや漢字が持つ意味を学習する
読み聞かせと音読で読解力を育てる
○読み聞かせの効果
親子で一緒に物語を味わう時間が、子どもの想像力と感受性、表現力、語彙力を伸ばします。
読み聞かせの後に「どう思った?」「続きはどうなると思う?」と問いかけることで、読解力や思考力も育ちます。
○音読の効果
文章を理解しながら読む練習になります。
黙読では読み飛ばしてしまう部分も、音読では一字一句丁寧に読むことになります。
読むリズムが身につき、自然と文章の構造をつかむ力が養われます。
毎日10分程度の音読を習慣にするだけで、確実に読解力が向上します。
文章を要約する練習をする
自分の言葉で言い換える練習をすることで、読解力と思考力、表現力を鍛えられます。
短い文章から始めて、「誰が・何を・どうした」を親に口頭で説明させることから始めましょう。
慣れてきたら、新聞記事や説明文を読んで、大事なポイントを箇条書きにする練習も有効です。
子どもとコミュニケーションを積極的に取る
○正しい言葉を使う
親が日常的に正しい文法や適切な言葉遣いをしていれば、子どもも自然と美しい日本語を身につけます。
「ら抜き言葉」や乱暴な言葉を使わないように意識しましょう。
○子どもに問いかけ・語りかけをする
一方的に指示するのではなく、「今日学校でどんなことがあった?」「それについてどう思う?」「なぜそう思ったの?」と対話を重ねることで、子どもは考えを言語化する練習ができます。
新しい体験や価値観に触れさせる
博物館や美術館、自然体験、様々な人との出会いなど、多様な経験が子どもの世界を広げます。
体験したことを言葉にすることで、表現の幅が広がり、想像力や感性も豊かになります。
体験後に「どこが面白かった?」など振り返りの会話をすることで、経験を言語化する力も育ちます。
家庭での小さな積み重ねが、頭の良さにつながる国語力を育てます。
注意点は、子どもに押しつけないことです。
楽しい家庭の雰囲気の中で、自然と子どもとの対話が増やせるといいですね。
小学生向け|国語力を伸ばすおすすめの本
文部科学省のWebサイトに読書の大切さについて触れられていますのでご紹介します。
「自ら本に手を伸ばす子供」を育てる
国語教育の中で,「自ら本に手を伸ばす子供」を育てることを考える必要がある。読書は,国語力を形成している「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」や「国語の知識」のいずれにもかかわり,これらの力を育てる上で中核となるものである。特に,すべての活動の基盤ともなる「教養・価値観・感性等」を生涯を通じて身に付けていくために極めて重要なものである。
文部科学省
国語力を伸ばす読書の方法
○多読よりも精読を大切にする
たくさん読むよりも、「1冊を深く理解する」ことが大切です。
分からない言葉があれば辞書で調べ、登場人物の気持ちを考えながら読み、印象に残った場面を振り返る。
このような精読を通じて、深い読解力が養われます。
○読み聞かせ後に子どもと本の内容を話す
「どんな話だった?」「主人公はどんな気持ちだったと思う?」「あなたが主人公だったらどうする?」と聞くことで、思考力と想像力が育ちます。
親子で感想を共有することで、子どもは自分の考えを言語化する練習ができます。
○親が読書する姿を見せる
子どもは親の行動を見て育ちます。
リビングで家族みんなが読書する時間を作ったり、親が読んだ本の面白さを話題にしたりすることで、自然と読書への関心が高まります。
低学年向け|国語力を伸ばすおすすめの本
○『ふたりはともだち』(アーノルド・ローベル)

がまくんとかえるくんの友情を描いた心温まる物語です。
短い章立てになっているので、読書が苦手な子どもでも読みやすく、友情の大切さや思いやりについて自然と考えることができます。
○『ぼくはめいたんてい(1) きえた犬のえ(新装版)』(マージョリー・W・シャーマット)
小さな探偵ネートが謎を解く推理物語です。
短くてテンポの良い文章で、子どもを飽きさせません。
謎解きの過程で論理的に考える力が養われ、推理しながら読むことで能動的な読書姿勢が身につきます。
中学年向け|国語力を伸ばすおすすめの本
○『はれときどきぶた』(矢玉四郎)

主人公の則安が書いた嘘の日記が現実になってしまうという奇想天外な物語です。
想像力を刺激する内容で、「もし自分の日記が現実になったら」と考えることで創造的思考も育ちます。
○『ぼくは王さま』(寺村輝夫)
わがままで愉快な王さまが巻き起こす騒動を描いた物語です。
王さまの行動を通して、常識やルールについて考えることができます。
ユーモアのある文章表現に触れることで、言葉の面白さや表現の豊かさを学べます。
高学年向け|国語力を伸ばすおすすめの本
○『モモ』(ミヒャエル・エンデ)
時間の価値と人間らしい生き方について深く考えさせられる名作です。
抽象的な概念を物語として理解する力が養われ、比喩や象徴を読み解く高度な読解力が身につきます。
読後に親子で「時間とは何か」「大切なものは何か」について話し合うことで、哲学的思考も育ちます。
○『ルドルフとイッパイアッテナ』(斉藤洋)
教養のある野良猫イッパイアッテナと、迷子になった飼い猫ルドルフの友情と成長の物語です。
登場人物の心情変化を丁寧に読み取る練習に最適で、逆境の中での成長や友情について深く考えることができます。
保護者向け|子どもの国語力を伸ばす参考書籍
○『将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!』(松永 暢史)
なぜ読書が重要なのか、どのように読書習慣をつけるのかを具体的に解説した一冊です。
10歳までの読書が将来の学力に与える影響や、年齢に応じた本の選び方、読書嫌いな子への対応法など、実践的なアドバイスが満載です。
まとめ|国語力は頭の良さの土台!小学生のお子さんの国語力を伸ばすおすすめの方法
この記事では、国語力と頭の良さの関係について、詳しく解説しました。
大切なポイントをおさらいしましょう。
- 「国語ができる人は頭がいい」と言われるのは、国語力が認知能力と非認知能力の両方を育てる土台となるから
- 国語力は、すべての学習の基礎であり、将来のコミュニケーション能力にも直結する
- 国語力がないとどうなるかというと、全教科の成績が伸び悩み、問題が発生したときに解決できず、適切なコミュニケーションも取れなくなってしまう恐れがある
- 小学生の国語力を伸ばすには、語彙力を鍛え、読み聞かせと音読を習慣にし、文章を要約する練習がおすすめ
- 家庭で出来るおすすめ方法は、「子どもと一緒に読書や読み聞かせの時間を持つ」「正しい言葉を使う」「子どもと対話する時間を大切する」「新しい体験をして子どもの世界を広げる」こと
- 本を読むときや読み聞かせのポイントは、多読よりも精読を大切にし、本を読んだ後に親子で内容を話し合うこと
「国語ができる人は頭がいい」という言葉の通り、国語力は一生の財産です。
国語力がないとどうなるかと悩む前に、今日から楽しく小学生の国語力を伸ばす取り組みを始めませんか。
お子さんの頭の良さを伸ばす無限の可能性を、国語力という土台でしっかりと支えてあげましょう。
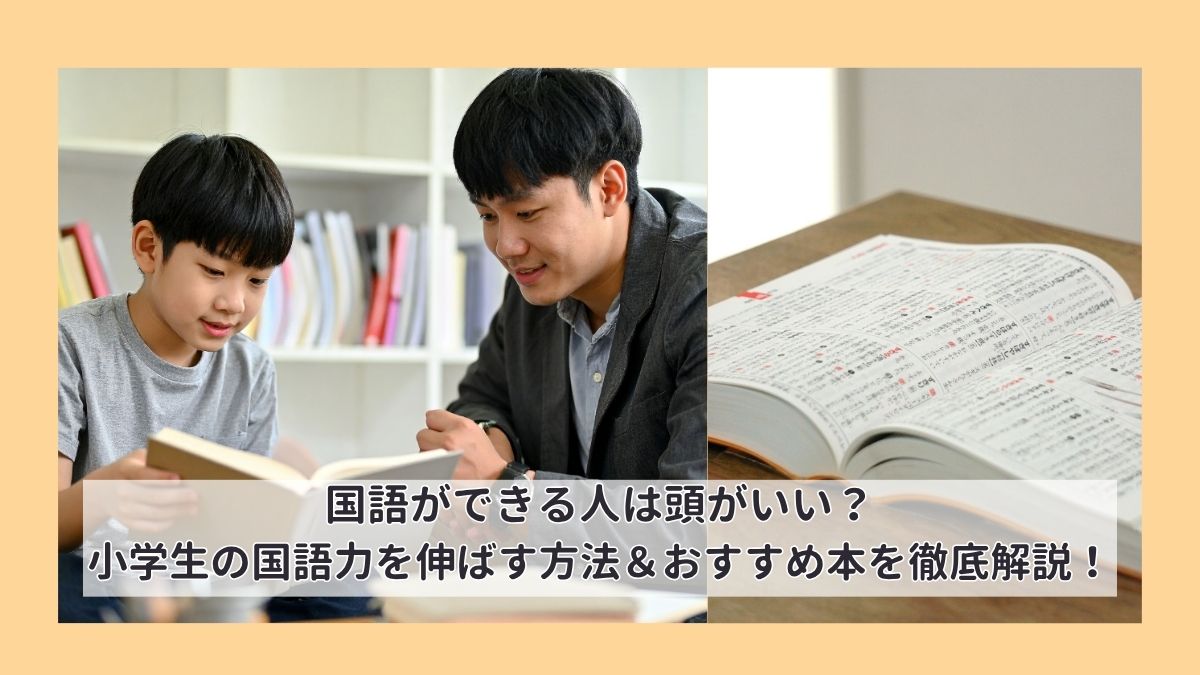





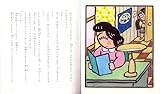






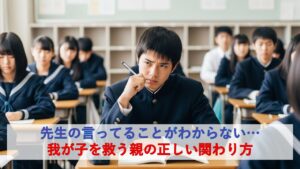
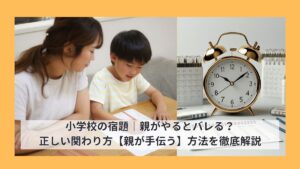
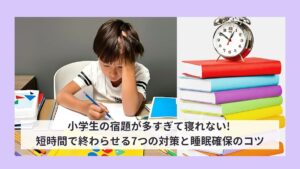
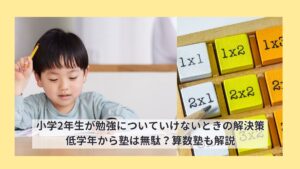
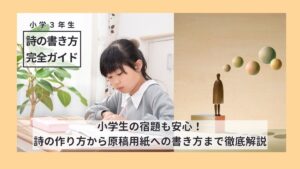
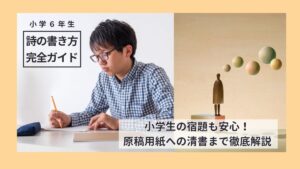
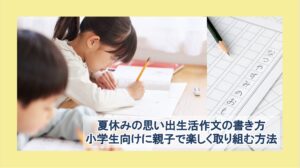
コメント