小学生のみなさん、詩の宿題が出されて困っていませんか?
- 「詩の書き方ってなんだっけ?」
- 「何から始めればいいのかわからない・・・」
そんな小学生(6年生)のみなさんとおうちの方に向けて、詩の書き方を分かりやすく解説します。
この記事を読めば以下の疑問を解決できます。
- 詩の書き方の基本的な手順を知りたい
- 6年生にぴったりのテーマは何?
- 詩に使える言葉の集め方は?
- 原稿用紙に清書する方法がわからない
詩に正解はありません!
自分らしい表現で、素敵な詩を完成させましょう。
この記事では、詩の書き方の基本から原稿用紙に清書する方法まで徹底解説しています。
一緒に楽しんで詩の宿題を進めていきましょう!
小学生(6年生)向け|詩の書き方の基本
詩の書き方の具体的な方法を解説する前に、ここでは小学生(6年生)向けに詩の基本を解説します。
おすすめの詩集も紹介していますので参考にしてくださいね。
自由詩と定型詩の違い
詩には大きく分けて「自由詩」と「定型詩」の2種類があります。
○定型詩
決まった文字数や韻律(リズム)に従って作る詩です。
俳句(5-7-5の17音)や短歌(5-7-5-7-7の31音)がその代表例です。
○自由詩
文字数や韻律に決まりがなく、自由に表現できる詩です。
現代では多くの詩人が自由詩を書いており、小学生の詩の宿題でも自由詩を求められることが多いでしょう。
この記事では、6年生のみなさんが取り組みやすい自由詩の書き方について詳しく解説していきます。
詩に正解はない!自由に表現しよう
詩の書き方で一番大切なのは、「正解はない」ということを理解することです。
詩は自分の気持ちや考え、感じたことを自由に表現する文学です。
他の人と同じである必要はありません。
あなたが感じたこと、思ったことを、あなたらしい言葉で表現すれば、それが素晴らしい詩になります。
最初は「うまく書けない」と思うかもしれませんが、何度も書いているうちに上達していくものです。
まずは完璧を目指さず、楽しんで書くことから始めましょう。
6年生におすすめの詩集紹介
詩を書く前に、いろいろな詩を読んでみることをおすすめします。
素敵な詩に触れることで、詩の魅力や表現の仕方を学ぶことができます。
以下に6年生におすすめの詩集を紹介していますので、是非読んでみてくださいね。
○『金子みすゞ名詩集』(金子みすゞ)
大正時代の童謡詩人、金子みすゞの詩集です。
「私と小鳥と鈴と」「大漁」など、やさしい言葉で深い感動を与える詩がたくさん収録されています。
身近なものを新鮮な視点で捉える表現が学べます。
○『まど・みちお詩集』(まど・みちお)
「ぞうさん」の作詞者としても有名な、まど・みちおの詩集です。
子どもの心を大切にした、温かく楽しい詩がたくさん読めます。
言葉の音やリズムの美しさを感じられる作品が多く、詩を声に出して読む楽しさを教えてくれます。

○『つたえたい美しい日本の詩(こころ)』シリーズ
現代から過去まで、日本の美しい詩を集めたシリーズです。
季節の詩、家族の詩、友情の詩など、さまざまなテーマの詩が収録されており、テーマ選びの参考にもなります。
小学生 詩の書き方 6つの基本ステップ
ここでは、6年生向けに詩の書き方の基本ステップについて解説します。
詩を書くときは、以下の6つのステップに従って進めると、スムーズに完成させることができます。
各ステップの詳細は以降の項目で解説します。
① テーマ・題材を決める
② 思い浮かんだ言葉をメモする
③ 集めた言葉を詩の形にする
④ 声に出して読んでみる
⑤ 少し時間をおいてから見直す
⑥ 原稿用紙に清書する
小学生の詩のテーマ選び|6年生らしい発想のヒント
ここでは、小学生の詩のテーマ選びについて解説します。
6年生らしいテーマのポイントも紹介していますので参考にしてくださいね。
身近なテーマから始めよう
詩を書くときは、身近で具体的なテーマから始めることをおすすめします。
○学校生活(友だち、部活動、行事、卒業への思い)
友だちとの思い出、部活動での体験、運動会や文化祭などの行事、そして卒業への複雑な気持ちなど、6年生ならではの体験を詩にしてみましょう。
○季節や自然(春夏秋冬の変化、好きな天気)
桜の花、夏の海、秋の紅葉、冬の雪など、季節ごとの特色を自分なりの言葉で表現してみましょう。
また、「雨の日の教室」「夕焼け空」「朝の空気」など、天気や時間帯に注目して詩を書くのもおすすめです。
○家族やペット
お母さんの手料理、お父さんの寝顔、犬の散歩、猫の昼寝など、普段は何気ないことでも温かい詩の題材になります。
○好きなもの・こと(スポーツ、音楽、食べ物)
自分が好きなことについて書くと、自然と気持ちがこもった詩になります。
サッカーボールを蹴る瞬間、好きな歌を聴いているときなど、「好き」という気持ちを詩で表現してみましょう。
6年生らしいテーマのポイント
小学校生活の集大成として、これまでの経験や成長を振り返ったり、中学校への不安や期待を表現したりすることで、6年生らしい深みのある詩が生まれます。
また、物事をより深く考えられるようになった6年生は、「なぜ?」「どうして?」という疑問を詩にすることもできます。
「なぜ空は青いの?」「どうして時間は戻らないの?」といった哲学的なテーマに挑戦してみるのも面白いでしょう。
テーマに沿った言葉集めのコツ|6年生におすすめの言葉
詩のテーマが決まったら、テーマに沿った言葉を集めましょう。
ここでは、準備しておくと便利な物や6年生らしい言葉選びのポイントについて解説します。
準備しておくと便利な物
言葉集めをするときに、以下のものを用意しておくと便利です。
○辞書や類語辞典
同じ意味でも、より詩に適した美しい言葉や、より正確な表現が見つかることがあります。
例えば、「きれい」という言葉も、「美しい」「麗しい」「清らか」など、様々な表現があります。
○下書き用の紙
思い浮かんだ言葉をどんどんメモするための紙を用意しましょう。
大きめの紙に、テーマを中心に書いて、そこから線を引いて関連する言葉を書いていく「マインドマップ」という方法もおすすめです。
五感を使った言葉・感情表現の見つけ方
詩をより豊かにするためには、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)を使った表現を取り入れましょう。
○視覚:色、形、大きさ、明るさなど
○聴覚:音、声、リズムなど
○嗅覚:においや香りなど
○味覚:味に関する表現
○触覚:手触り、温度、感触など
感情表現も詩には欠かせません。
「嬉しい」「悲しい」だけでなく、「胸がどきどきする」「心が踊る」「涙がこぼれそう」など、具体的な表現を使ってみましょう。
6年生らしい言葉選びのポイント
6年生になると語彙も豊富になり、より複雑な感情も表現できるようになります。
子どもっぽすぎず、でも背伸びしすぎない、自分らしい言葉を選ぶことが大切です。
良い例:
- 「友だちとの思い出が宝物のようにきらめいている」
- 「卒業という言葉が、そっと心に響く」
小学生向け|集めた言葉を詩の形にする方法
詩のテーマに沿った言葉を集めた後は、いよいよ詩を作ってみましょう!
6年生らしい詩を書くための表現技法や詩の完成度を高める方法について解説します。
詩で使える表現技法の紹介
詩をより美しく、印象的にするための表現技法をいくつかご紹介します。
○比喩(ひゆ)
物事を他のものに例えて表現する技法です。
・直喩:「〜のような」「〜みたいな」を使う
例:「雲が羊のように空を歩いている」
・隠喩(暗喩):「〜のような」を使わずに例える
例:「空に浮かぶ白い羊たち」
○擬人法
人間でないものを人間のように表現する技法です。
例:「花が微笑んでいる」「風が歌を歌っている」
○反復
同じ言葉や表現を繰り返して、リズムや印象を強める技法です。
例:「ありがとう、ありがとう、友だちよ」
○対比
反対の意味を持つ言葉や表現を使って、印象を強める技法です。
例:「明るい未来と暗い過去」「笑顔の向こうの涙」
声に出して読んで完成度を高める
詩は文字で読むだけでなく、声に出して読むことでより深く味わえます。
実際に声に出して読んでみて、以下のことを確認しましょう。
- 読みにくい部分はないか
- リズムは良いか
- 言葉の響きは美しいか
- 感情がうまく伝わるか
少し時間をおいてから見直す
詩を書いた直後は、自分の気持ちが高ぶっているため、客観的に見ることが難しいものです。
一日か二日時間をおいてから読み返すと、新鮮な気持ちで自分の詩を評価できます。
見直すポイント:
- 伝えたいことがうまく表現されているか
- 不要な言葉はないか
- もっと良い表現はないか
- 誤字脱字はないか
原稿用紙の使い方|詩をきれいに清書するルール
詩が完成したら原稿用紙に清書しましょう!
ここでは、小学生に向けて原稿用紙への詩の書き方の基本ルールや注意点など詳しく解説します。
小学生が知っておきたい原稿用紙の基本ルール
原稿用紙に詩を書くときは、以下の基本ルールを守りましょう。
○題名の書き方
- 原稿用紙の1行目に3マス空けて題名を書く
○氏名の書き方
- 2行目の下部に学年・組・氏名を書く
- 例)六年一組○山田○太郎○ (○は空白)
○本文の書き方
- 3行目を飛ばして4行目から本文を書き始める
- 各行の始めは1マス空ける場合が多い
- 句読点は使わないことが多い
- 行の最後で文が終わらない場合は、次の行に続ける(その場合は1マス空けずに続きを書く)
詩を清書するときの注意点
○文字の大きさと濃さ
- 文字は適度な大きさで、濃くはっきりと丁寧に
○行間の使い方
- 場面が変わるところでは1行空けることもある
- 全体のバランスを考えながら書く
小学生(6年生)向け|詩の参考例
ここでは、学校生活をテーマにした詩の例をご紹介します。
最後の運動会
赤い帽子をかぶって 走った六年間
今日が最後の運動会
仲間の声援が 背中を押してくれる
転んでも 立ち上がって また走る
ゴールテープの向こうに 新しい季節が待っている
でも今は この瞬間を 大切にしたい
六年生の 最後の運動会
この詩では、運動会という具体的な行事を通して、卒業を控えた6年生の複雑な気持ちを表現しています。
「転んでも立ち上がって」という部分で成長への意志を、「この瞬間を大切にしたい」という部分で今を大切にする気持ちを表現しています。
詩の宿題に困ったときの解決法
ここでは、小学生が詩の宿題を進めるなかで行き詰まったときの対処法や、おうちの方ができるサポートについて解説します。
行き詰まったときの対処法
詩を書いていて行き詰まったときは、以下の方法を試してみましょう。
○一度書くのをやめて、散歩や読書をする
煮詰まったときは、いったん詩から離れて散歩をしたり好きな本を読んだりすることで、新しいアイデアが浮かんでくることがあります。
○友だちや家族と話してみる
テーマについて友だちや家族と話してみることで、新しい視点が見つかるかもしれません。
○テーマを変えてみる
どうしても書けないときは、思い切ってテーマを変えてみましょう。
無理に書こうとするより、書きたいと思えるテーマに変える方が良い詩ができることがあります。
おうちの方ができるサポート
お子さんが詩の宿題で困っているときの、おうちの方のサポート方法をご紹介します。
○子どもの話を聞く
まずは、お子さんがどんなことを詩にしたいのか、何に困っているのかを聞いてあげましょう。
話すことで、子ども自身が自分の考えを整理できることがあります。
○一緒に体験を振り返る
家族での思い出や、最近の出来事について一緒に話してみましょう。
「あのときどう思った?」「何が一番印象に残ってる?」などの質問で、子どもの感情を引き出してあげてください。
○無理に手伝いすぎない
詩は子ども自身の感情や体験を表現するものです。
大人が手伝いすぎると、子どもらしさが失われてしまいます。
あくまでもサポート役に徹し、子ども自身が書けるように支援してあげてください。
まとめ|詩の書き方をマスターして宿題も安心
詩の書き方について、小学生(6年生)向けにテーマの選び方から原稿用紙への清書の方法まで詳しく解説してきました。
重要なポイントをもう一度まとめてみましょう。
○詩の書き方で大切なこと
- 詩に正解はないこと
- 自分らしい表現を大切にすること
- 身近なテーマから始めること
- 五感を使った豊かな表現を心がけること
- 原稿用紙の基本ルールを押さえて丁寧に清書すること
6年生のみなさんにとって、詩は自分の気持ちや体験を表現する素晴らしい方法です。
最初はうまく書けないと感じるかもしれませんが、何度も書いているうちに必ず上達します。
この記事を読んで実践すれば、スムーズに詩の宿題が完了できるはずです。
おうちの方も、お子さんが詩を通して自分自身と向き合い、表現力を豊かにしていく過程を温かく見守ってください。
この記事を参考に、ぜひ小学生らしい素敵な詩を完成させてくださいね。
詩の宿題をきっかけに、詩の世界を楽しめますように。
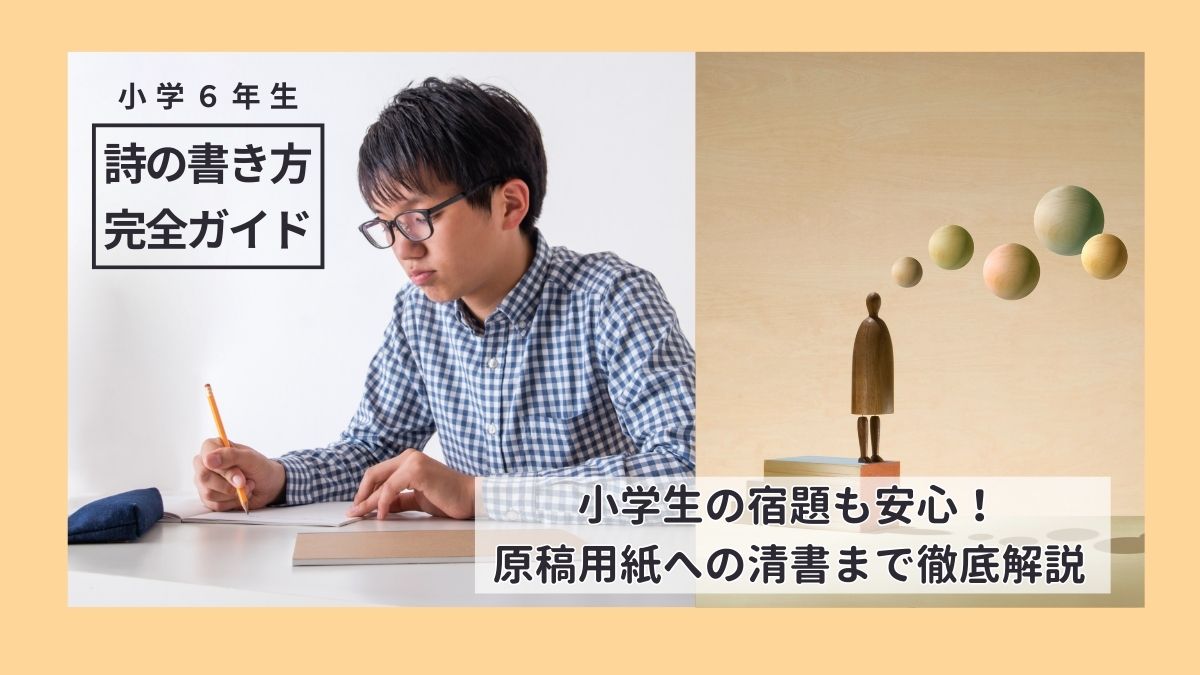












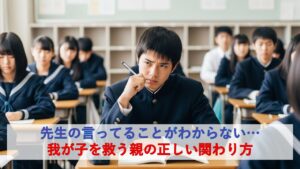
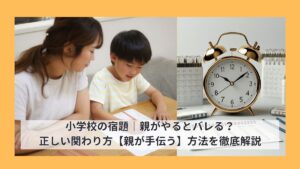
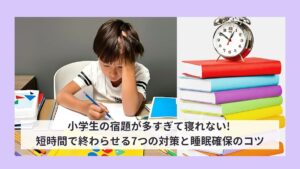
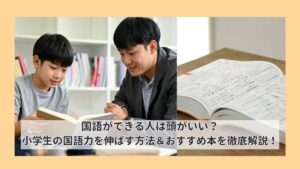
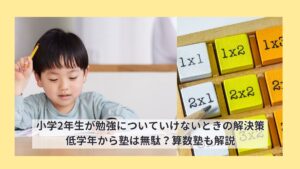
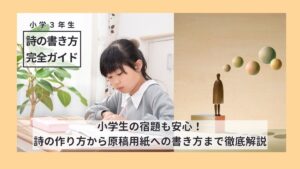
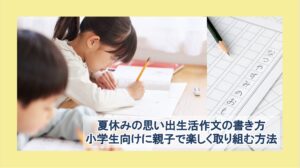
コメント