3歳になってもトイレ嫌がる…。
泣いて拒否されたり、めんどくさがる姿についイライラしてしまう…。
毎日声をかけてるのにトイレトレーニングがうまく進まない。
元保育士の私も3歳児を育てる母として同じ悩みを経験しました。
この記事では、保育士としての経験と、母としての子育てを通じた実体験をもとに、以下の内容を詳しく解説します。
・3歳がトイレトレーニングを嫌がる本当の理由
・3歳がトイレを嫌がる!泣く!めんどくさがる!理由別トイレトレーニングの遊び化アイデア
・3歳がトイレを嫌がる・泣く状態を成功体験にするための「ごほうび法」活用術
・トイレを嫌がる3歳への、親のイライラ解消に最適なツール
3歳トイレトレーニング嫌がる本当の理由とは?
3歳の子がトイレトレーニングを嫌がる理由を詳しくみていきましょう。
保育園ではできるのに家ではトイレ嫌がる?その謎の正体
保育園で嫌がらずトイレができる3歳のAちゃん。
ところが家に帰ると、トイレに誘っただけで「いや!」と泣いて拒否。
保護者の方は「保育園ではできるのになぜ家ではできないの?」と悩んで相談を受けました。
これは決して珍しいことではありません。
実は、甘えが出やすい「家庭」ならではの心理的ハードルが存在するのです。
保育園では「お友達もやっているから」「先生がいるから」という安心感がありますが、家庭では親への甘えから「今はやりたくない」「お母さんに構ってほしい」という気持ちが強く表れます。
この現象を理解することで、「家ではできない子」ではなく「保育園で頑張っている子」として捉え直すことができ、アプローチも変わってきます。
3歳トイレトレーニング嫌がる「理由別チェックリスト」
3歳の子がトイレトレーニングを嫌がる原因について、理由別にチェックしていきましょう。
身体的な理由
便座が高くて不安/足が浮いて落ち着かない
3歳の身長では、多くの便座で足が床につかず宙に浮いてしまいます。
この不安定感が恐怖心を生み、トイレ嫌いの原因となることがあります。
トイレの音やにおいへの過敏反応
敏感な子は、換気扇の音や水の流れる音、トイレ特有のにおいに過度に反応し、トイレ空間自体を避けたがることがあります。
誘導タイミングがズレている
おしっこが出る前のサインを読み取れずに誘うと、「出ない時に座らされる」という不快な経験が積み重なり、トイレを嫌がるようになります。
心理的な理由
失敗した記憶がトラウマになっている(泣いて拒否)
一度でも叱られたり、失敗を強く指摘されたりした経験があると、それがトラウマとなってトイレ全体を怖がるようになることがあります。
「もう赤ちゃんじゃない」自立心と甘えたい気持ちの葛藤
3歳は自立心が芽生える時期。「お兄さん・お姉さんになりたい」気持ちと「まだ甘えていたい」気持ちが混在し、複雑な感情を抱えています。
「めんどくさがる」「やりたくない」の感情
今やっている遊びを中断してトイレに行くことを面倒に感じたり、単純に「やりたくない」という感情が強く出る時期でもあります。
環境的な理由
親の焦りやイライラが子どもに伝わっている
親の「もう3歳だから早くできるようになってほしい」という気持ちや焦りは、敏感な子どもにはプレッシャーとして伝わります。
他の子と比較されるストレス
「お友達は3歳でもうできていたのに」という比較は、子どもの自信を失わせ、トイレトレーニングへの意欲を削いでしまいます。
一貫性のない声かけで混乱
家族内でアプローチが統一されていないと、子どもは混乱し、どう行動すべきかわからなくなってしまいます。
3歳トイレトレーニング嫌がる子のサインを読み解く「保育士の観察術」
拒否の瞬間の表情=怖い?怒ってる?甘えてる?
子どもがトイレを嫌がる時の表情をよく観察してみてください。
眉間にしわを寄せて怖がっているのか、口をとがらせて怒っているのか、上目遣いで甘えているのか。
表情によって原因と対処法が変わってきます。
時間帯ごとの傾向(朝は不機嫌/夜は甘えが出やすい)
朝起きたばかりは機嫌が悪く、夜は疲れて甘えが出やすいなど、時間帯による傾向を把握することで、効果的なタイミングを見つけることができます。
我が子のサインに気づいた3つのポイント(実体験)
私の子どもの場合、①カーテンやドアの後ろに隠れる、②足をもじもじさせる、③急に静かになる、という3つのサインがありました。
我が子特有のトイレサインを観察してみて下さい。
このサインを見逃さずキャッチすることで、成功率が格段に上がりました。
3歳トイレ嫌がる・泣く・めんどくさがる 理由別トイレトレーニングの遊び化アイデア
3歳の子がトイレを嫌がる理由別に、遊び化のアイデアを解説します。
実際に保育士として経験した実例もご紹介します。
泣く子には「安心できるトイレ空間を」
好きなキャラクターで「トイレは安全な場所」に
子どもが好きなキャラクターのポスターやステッカーをトイレに貼り、「アンパンマンがいるから大丈夫」「くまさんが応援してくれてる」という安心感を作り出しましょう。
小ステップ作戦(見る→座る→成功)
いきなり「トイレでする」ではなく、「トイレを見に行こう」→「便座に座ってみよう」→「座れたらOK」というように、小さな成功を積み重ねます。
実例:保育園で怖がりだったBくんの克服ストーリー
保育園でトイレを怖がっていた3歳のBくん。
その理由は、「トイレが広くて怖い」と感じていたからでした。
2歳児クラスから3歳児クラスに進級し、新しい環境に不安を感じていたのです。
まずはクラスみんなで“お部屋探検”をして、トイレも一緒に見に行くところからスタート。
次に、トイレに行くことへの不安を和らげるため、大好きな電車のミニカーを持ってトイレに行くようにしました。
「電車さんもトイレを見に行くんだって!」という声かけをすると、1週間ほどでトイレに入れるようになり、2週目には便座に座れるようになりました。
めんどくさがる子には「移動・行動をゲーム化」
「鏡を見に行こう」→トイレのついで作戦
「トイレ行こう」ではなく、「鏡でかっこいい顔見せて」「手を洗いに行こう」など、別の目的でトイレエリアに誘導し、ついでにトイレを提案する方法です。
トイレまで10秒競争/お気に入りの音楽に合わせて行く
「ママと競争しよう!10秒でトイレまで行けるかな?」や、好きな歌を歌いながらトイレに向かうことで、移動自体を楽しい時間に変えます。
実例:めんどくさがる子Cくんが行きたくなった理由
遊びに夢中で、トイレに行きたがらずめんどくさがる3歳のCくんには、「忍者修行でトイレ忍術を覚えよう!」という設定を取り入れました。
足音を立てずにトイレまで歩く、座っている間は忍者のポーズをするなど、遊びの延長としてトイレトレーニングを取り入れたことで、Cくんはめんどくさがる姿が減り、自分からトイレに行くようになりました。
※ただし、子どもが集中して遊んでいる最中に急に中断させるのは、かえって逆効果になることもあるため、あまりおすすめできません。
自立心が強い子には「選ばせる・任せる」
「どのパンツにする?」「どの歌でトイレ行く?」
自分で決めたい気持ちが強い子には、選択肢を与えることが効果的です。
「今日はどのパンツがいい?」「どの歌を歌いながら行く?」など、自分で選んだという満足感を大切にします。
ぬいぐるみの先生役をさせ、リーダー気分で促す
「クマさんがトイレの仕方がわからないから、教えてあげて」という設定で、子どもを先生役にします。
人に教えることで、自分もより意識してトイレに取り組むようになります。
実例:しっかり者Eちゃんのお姉さん作戦
年下の子のお世話が好きなお姉さんタイプの3歳Eちゃんには、「お手本になってね」という声かけが効果的でした。
年下の子の前では張り切ってトイレに行き、その成功体験が自信につながって、一人の時もできるようになりました。
家庭でもできる保育士流アプローチ
上記以外にも家庭でできるアプローチ方法がいくつかあります。
私が保育士として実践していたことを紹介します。
「みんなでトイレ大会」=家族やぬいぐるみの集団効果
家族みんなでトイレタイムを作ったり、ぬいぐるみたちも一緒にトイレに行く設定にしたりすることで、「みんなやってる」という安心感と楽しさを演出します。
実際に我が家では娘の好きなキャラクターをトイレに並べて「順番待ってます」という設定にしたり、「応援してるよ!」という声掛けをしたりしていました。
遊びを取り入れたことで、娘の「いや」が少しずつ減り、「くまちゃん待っててね」と自分からすすんで座れるようになりました。
楽しいルーティンづくり+発達に合った声かけ
トイレの前後に決まった歌を歌う、手洗いの時に特別な石鹸を使うなど、楽しいルーティンを作ることで、トイレタイム全体が楽しい時間になります。
「トイレに行こう」と声掛けするよりも、声掛けをリズミカルにしたり歌ったりする方が指示が入りやすい場合もあります。
イライラを手放すために「成功より安心感を優先」
「毎日声を掛けているのに今日もダメだった… 」そんな気持ちが続き、私自身もイライラした経験があります。
ですが、結果を急がず、「トイレは安心できる場所」「失敗しても大丈夫」という安心感を最優先にすることが大切だということを経験から改めて学びました。
「もう3歳だから早くトイレを成功させたい」という親の焦りは子にも伝わってしまいます。
私自身わかっていても、内心焦っていたのが子どもに伝わってしまい余計にトイレを嫌がる原因になっていました。
そんな中子どもとの間で合言葉にしたのが、「失敗は成功のもと」という言葉でした。
考え方一つで親の気持ちも楽になり、子どもにも良い影響を与えます。
この一言があるだけで、私の気持ちもラクになり、娘も「できなかった…」と落ち込まずに、「せいこうのもとよね」と前向きな声を出すようになってくれました。
小さな言葉の力って、本当に大きいなと実感しました。
3歳トイレ嫌がる・泣くを成功体験に!「ごほうび法」活用術
トイレに行けたらシールを貼る――そんな「ごほうび法」はよく知られていますが、しばらくすると子どもが飽きてしまい、効果が続かなくなった…という経験はありませんか?
この記事では、そんな悩みに応えるために、ステップアップ式の「段階的ごほうび法」について詳しく解説していきます。
段階的ごほうびステップ(保育園でも実証済)
接近期:トイレに向かう →「勇気シール」
まずはトイレに向かうことができただけで「勇気シール」を貼ります。
結果に関係なく、チャレンジしたことを認めることが大切です。
挑戦期:便座に座る →「チャレンジスタンプ」
便座に座ることができたら「チャレンジスタンプ」を押します。
出る出ないは問わず、座れたことを評価します。
成功期:できた →「がんばったメダル」
実際にトイレでできた時は「がんばったメダル」を授与。
大げさなくらい喜んで、達成感を高めます。
自立期:自分から行く →「お兄さん・お姉さん認定」
自分からトイレに行けるようになったら、「お兄さん・お姉さん認定証」を作って渡します。
成長を実感できる特別な演出が効果的です。
ごほうび依存を防ぐポイント
モノ→体験→関係性に変化:ごほうびの意味を変えていく
まずはシールやスタンプなど、目に見える“モノ”のごほうびからスタート。
慣れてきたら、「一緒に好きな絵本を読む」「おうちで特別な遊びをする」などの“体験型”のごほうびへ。
そして最終的には、「ママが嬉しそうに笑ってくれた」「ぎゅっとハグしてくれた」といった、関係性のごほうびへと移行していきます。
子どもにとって、「大好きな人に喜んでもらえる」という体験が、何よりも大きなごほうびになるのです。
ランダムに与える(毎回ではなく、時々)
毎回ごほうびを与えるのではなく、時々にすることで、ごほうび依存を防ぎながら、もらえた時の喜びを大きくします。
本人の達成感に目を向けさせる声かけ例
「シールがもらえて嬉しいね」ではなく、「自分でできて、どんな気持ち?」「頑張った自分はすごいね」という声かけで、内発的な達成感に注目させます。
我が子の失敗から学んだこと
ごほうび依存に陥った過去→軌道修正の工夫
私自身、最初はシールをごほうびにしていましたが、ついついあげすぎてしまい、「シールだけ貼りたい」と言うようになってしまったことがあります。
そこで、シールをあげる頻度を徐々に減らし、その代わりに「できた自分に拍手!」や「ママとハイタッチ」など、達成感や関わりを感じられるごほうびにシフトしていきました。
すると、少しずつ「トイレに行けた自分」への自信が育ち、自然とごほうびがなくても行けるようになっていったのです。
「ママの笑顔が嬉しい」=一番のごほうびだった気づき
最終的に気づいたのは、子どもにとっていちばん嬉しいごほうびは、大好きなママやパパの笑顔だったということです。
シールやおもちゃなどの“モノ”よりも、「うれしい!」「すごいね!」と心から喜んでくれる姿のほうが、子どもの心にまっすぐ届いていました。
「ママが喜んでくれるから、またやりたい」と思える。
そんな気持ちこそ、トイレトレーニングの本当の原動力だったのだと実感しています。
トイレ嫌がる3歳へのイライラ解消「こどもちゃれんじ」で再スタート!
「3歳なのにトイレを嫌がる」という親のイライラや焦りは、不思議と子どもにも伝わり、緊張や不安につながってしまうものです。
トイレを嫌がる姿に思わずイライラしてしまう…そんな時こそ、楽しく前向きに再チャレンジできる環境づくりが大切です。
保育士目線で見た「こどもちゃれんじ」の魅力
そんなときにおすすめなのが、遊び感覚でトイレ習慣を身につけられる教材、『こどもちゃれんじ』です!
発達理論に基づいた段階的プログラム
子どもの発達段階に応じて、無理なくステップアップできるよう設計されています。
このアプローチは、保育現場でも大切にされている考え方と一致しており、子どもの「できた!」を積み重ねることに重きを置いている点が特徴です。
飽きずに続く仕掛け(知育玩具・動画連携)
トイレトレーニング専用のしまじろうのアニメ動画と知育玩具が連動して、子どもが“見て・触って・真似して”学べる仕掛けが満載。
いろいろな角度からアプローチできるので、飽きずに楽しく続けられる工夫がしっかり詰まっています。
例えば「こどもちゃれんじぽけっと(2歳・3歳向け)」のコースでは、「しまじろう みみりんと いっしょにトイレ」は、トイレを列車に見立てた楽しい歌や、しまじろうたちの応援ボイス付き。ボタンを押して楽しむことで、トイレがワクワクする場所に変わります。
また、同じく2歳・3歳コースの「トイレでできたよ!ポスター&シール」は、トイレに貼って遊べるごほうびアイテム。
トイレに行けたらシールを貼って列車を伸ばしていける仕組みで、「またやりたい!」という意欲につながります。
こどもちゃれんじで楽しい再チャレンジを
キャラクターとの一体感=安心できる存在
しまじろうなどの親しみやすいキャラクターが一緒にトイレトレーニングを頑張ってくれることで、子どもは安心感を得られ、「一人じゃない」という心強さを感じることができます。
家庭と保育園で共通アプローチできる
多くの保育園でも活用されている教材なので、家庭と保育園で一貫したアプローチが可能になり、子どもの混乱を避けることができます。
オムツ外しのイメージトレーニング💖
— なりきり読み聞かせ放送局 (@yomikikaseyout) June 12, 2019
トイレは楽しい所だよ🎶
【オムツはずし】『トイレッシャ しゅっぱつ!』こどもちゃれんじ 絵本 読み聞かせ https://t.co/CKH3HFRMZD @YouTubeより#しまじろう #おむつはずし #トイレトレーニング #こどもちゃれんじ #読み聞かせ pic.twitter.com/65whrPpgns
さすがこどもちゃれんじ!!と思った教材!
— えむえむ (@emuemu0205) July 23, 2024
トイトレの絵本が届いてから、ぬいぐるみ座らせたり、自分が座ったり、トイレへの意識めっちゃ上がった!!!! pic.twitter.com/7nkes8FF5P
こどもちゃれんじ届くといつも自分で持って入って「あけて!」言う息子。
— ちぇる•°✻ 3y🦖+1y🎀 (@kyo_lcosme) April 27, 2024
保育園でも去年からトイトレしてるけど(おしっこはほぼok)いいの入ってたから貼ってみた、、、
シール貼るの大好きだから出てもまたすぐトイレ行く!言うけど(笑)
自分で脱いで座ってトイレして…。
成長ってすげぇや🙄 pic.twitter.com/FtXljhEUWq
📌 より詳しい内容は別記事にて紹介中! → [トイレトレーニングに効果的な『こどもちゃれんじ』の詳細はこちら]

3歳トイレトレーニング嫌がる!泣く!めんどくさがる!解決策【まとめ】
トイレトレーニングを嫌がる・泣く・めんどくさがる。
これらはどれも3歳ぐらいの子どもにみられる成長過程です。
大切なポイントを以下でまとめています。
①嫌がる理由の正しい見極め
「泣く・嫌がる・めんどくさがる」の裏にある本音をキャッチしましょう。
子どもがトイレを嫌がる理由は様々です。
身体的・心理的・環境的な要因を冷静に分析し、我が子の本当の気持ちを理解することが解決の第一歩です。
②遊び化と声かけ工夫
泣く子には安心感を、めんどくさがる子にはゲーム性を、自立心の強い子には選択権を、それぞれの性格に合わせたアプローチをしましょう。
親の焦る気持ちやイライラは子どもにも伝わってしまいます。
結果を急がず、トイレトレーニングを楽しい時間に変えましょう。
③3歳トイレトレーニング再チャレンジには教材活用がおすすめ
『こどもちゃれんじ』で自信と成功体験を。
「嫌がる!泣く!めんどくさがる!」と行き詰まった時は、信頼できる教材の力を借りることも大切です。
専門的な知識に基づいた教材で、親子ともに新鮮な気持ちで再スタートを切りましょう。
焦らず、イライラせず、笑顔で寄り添いながら、親子で一緒に前進していきましょう!

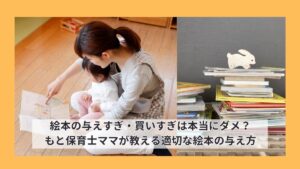

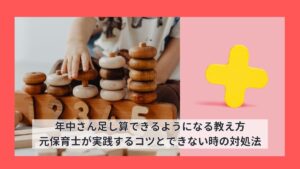


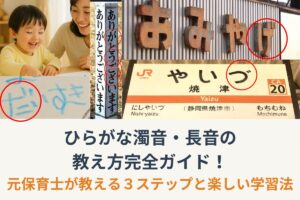
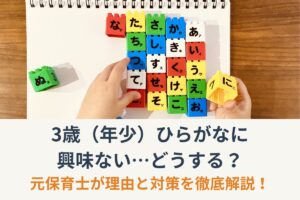
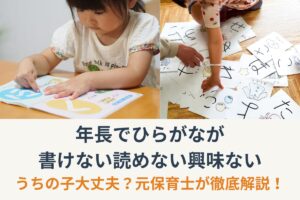
コメント