「年中さんに足し算っていつから教えるの?」
「うちの子、足し算ができなくて心配…」
「足し算ができる子とできない子では、それぞれどんな教え方が合っているの?」
保育士で年中さんの担任をしていた際にそんな悩みを抱える保護者の方の声をよく聞いていました。
保育現場で培った経験をもとに以下を詳しく解説していきます。
・年中の足し算を始める適切な時期と発達の目安について
・年中の足し算の教え方として効果的な5つのステップ
・年中の足し算ができない時の原因別対処法について
・年中で足し算ができる子の特徴とサポート方法について
・年中さんの足し算学習におすすめの教材「こどもちゃれんじ」について
年中さんの足し算はいつから始める?【発達の目安を保育士が解説】
年中さんの足し算学習を始める目安を発達の観点から詳しく解説します。
保育現場で見てきた年中さんの数の理解と発達
保育士として多くの年中さんを見てきた経験から、4歳児の数への理解は段階的に発達していきます。
4歳前半(年中になったばかり): 1~10まで数える、物の個数を理解する段階です。
多くの子どもたちは数唱はできても、まだ数量の概念が曖昧な状態です。
4歳後半~5歳: 簡単な合成・分解の理解が始まります。
「3個と2個で5個になる」といった概念を、具体的な物を操作しながら理解できるようになってきます。
最も重要なのは、個人差が大きい時期だということです。
同じクラスでも発達の差は自然なことなのです。
足し算を始める判断基準(保育士目線)
年中さんが足し算を始められるかの判断基準として、以下の3つを重視していました。
数の概念がしっかりしているか: 単に数唱ができるだけでなく、5個の積み木を正確に数えて「5個だね」と理解できる状態です。
集中して活動に取り組めるか: 年中さんの集中力は10~15分程度。
短時間でも最後まで一つの活動に取り組める姿勢があるかを見ます。
数に興味を示しているか: 「何人家族?」「おやつは何個もらえる?」など、日常生活の中で数に関心を持っている様子が見られることが大切です。
【体験談】わが子(3歳半・年少)の現在の様子
わが家の3歳半の息子は、現在10まで数えることはできますが、まだ数量の理解は発展途上です。
このような段階の子どもには、足し算を無理に教えるのではなく、日常生活の中で自然に数に親しむ機会を大切にしています。
年中さんへ向けての準備として、今は「数えること」と「数量を実感すること」を遊びの中で楽しく体験させることが一番重要だと感じています。
年中さん足し算の教え方【保育士が実践した5つのステップ】
実際に年中さんのクラスで実践していた足し算の教え方を5つのステップで解説します。
ステップ1:具体物で数の合成を体験
年中さんの足し算の教え方として、まず具体物を使った数の合成から始めます。
おやつ配りでの自然な数の合成体験 :
「Aちゃんのお皿にクッキーが2個あるね。あと1個足すと何個になるかな?」と声をかけながら、実際に子どもの目の前でクッキーを追加します。
ブロック遊びを活用した方法 :
「こっちに3個、あっちに2個あるよ。全部でいくつかな?」と問いかけながら、子ども自身に数えさせます。
遊びの中での学びは、子どもにとって負担なく楽しく取り組めます。
ステップ2:指を使った足し算
足し算の教え方のコツとして、指を使った年中の足し算は、最も身近で分かりやすい方法です。
片手から始める理由 :
まず5までの数をしっかりと理解させるためです。
いきなり両手を使うと混乱する子が多いので、「3+1」「2+2」など片手で完結する問題から始めます。
視覚的理解を促す声かけ方法 :
「3本の指を出して、もう1本足してみよう。今度は何本になった?」と段階を追って確認します。
年中さんに向けて今からできること:
「お箸を2本、スプーンを1本で、全部で何本かな?」といった自然な声かけを心がけることです。
ステップ3:身近な物を活用した足し算ゲーム
宝探し足し算ゲーム:
「お部屋から赤いブロックを2個、青いブロックを3個探してきて!見つけたら全部で何個か教えてね」と宝探し形式にします。
子どもが自分で集めた物を数えることで、より主体的に足し算に取り組めます。
お店屋さんごっこで足し算:
「いらっしゃいませ!りんごが2個とバナナが1個で、お買い物は全部で何個ですか?」とお店屋さんごっこの中で足し算クイズを出します。
遊びの要素が強いので、子どもは楽しみながら自然に計算します。
動作付き足し算チャレンジ:
「手をパチパチ2回叩いて、足をドンドン3回踏んで。全部で何回音を出したかな?」と体を使った足し算ゲームにします。
体験型なので記憶に残りやすく、楽しく学習できます。
ステップ4:簡単な数式への移行
式の書き方より理解を重視する:
年中さんの段階では、「2+1=3」という式を書けることよりも、2と1を合わせると3になるという概念の理解を最優先にします。
子どもが混乱しない進め方 :
まず口頭で「2と1で3だね」と確認し、慣れてきてから「2たす1は3」という言い方を導入します。
ステップ5:継続的な練習で定着 【保育現場での継続方法】
遊びの中での自然な反復 :
毎日の遊びの中で意識的に数の問題を取り入れます。
様々な場面で応用できるよう工夫することが重要です。
例えば、「今日の⚪︎⚪︎組と⚪︎⚪︎組のお休みのお友達を合わせると何人?」のように毎日の保育で継続して取り入れることができます。
褒めるタイミングとポイント:
正解した時だけでなく、一生懸命考えている過程も大いに褒めます。
「よく考えているね」「数えるのが上手だね」といった声かけが、子どもの学習意欲を高めるのです。
年中さんが足し算できない時の対処法
年中さんが足し算できない場合、大きく3つのパターンがあります。
以下で詳しく解説します。
パターン1:数の概念が曖昧な場合
数唱はできるが数量理解が不十分 な子は、年中さんクラスに必ず何人かいました。
「いち、に、さん…」と10まで言えるのに、実際に5個の積み木を数えると数えすぎてしまったり、同じものを二度数えてしまったりします。
具体的な改善アプローチとして、まずは5までの数を確実にマスターすることから始めます。
毎日のおやつの時間に「今日はクッキーが3個だね。いち、に、さん」と一緒に数え、3という数量の実感を積み重ねます。
同学年でも大きな個人差があることを理解して、決して他の子と比較しないことが重要です。
それぞれの子どもの発達段階に合わせたサポートが必要です。
パターン2:集中力が続かない場合
適切な活動時間の設定:
年中さんの一回の学習は5~10分程度に留め、子どもが「もう少しやりたい」と思うタイミングで終わらせます。
そうすることで「またやりたい」につながっていきます。
興味を持続させる工夫:
子どもの好きなキャラクターや遊びを取り入れたり、時には歌に合わせて数を数えたりします。
無理強いは逆効果:
子どもが明らかに集中できていない時は「今度また一緒にやろうね」と切り上げることも大切です。
気持ちが向かない時に続けても苦手意識につながってしまい逆効果です。
パターン3:プレッシャーを感じている場合
年中で足し算ができない場合でも、比較しない声かけ を徹底します。
「○○ちゃんは足し算ができるのに」といった比較は絶対にNG。
代わりに「昨日より上手に数えられたね」など、その子自身の成長に着目した声かけを心がけます。
自信を育む関わり方(具体的な褒め方のコツ)として、小さな成功も見逃さずに褒めることが重要です。
足し算ができない事を指摘するのではなく、「2まで数えられたね!」「指をちゃんと使って考えているね!」など、具体的で的確な褒め言葉をかけます。
成功体験を積み重ねていくことで自信がつき、少しずつ足し算ができるようになり、レベルアップしていきます。
その子が確実にできる問題から始めて成功体験を積み重ねていきましょう。
年中で足し算できる子の特徴とサポート方法
年中で足し算ができる子には、いくつかの共通点がありました。
以下で詳しく解説します。
できる子の共通点(保育士の観察より)
・数への興味・関心が高い:
日常生活の中でも自然に数を意識しています。
・具体的操作を十分に経験している:
ブロック遊びやお手伝いなど、物を数えたり分けたりする経験が豊富な子は、数の概念がしっかりと身についていきます。
・周囲の大人が適切にサポートしている:
子どもの興味関心のサインを見逃さず、足し算ができる子が継続的に楽しみながら学習できる環境も大切です。
さらに伸ばすためのアプローチ
年中で足し算できる子には、適度な挑戦を用意することが大切です。
繰り上がりへの準備 :
「7+4」のような少し難しい問題も、具体物を使いながら挑戦させます。
より複雑な問題への挑戦方法 :
「3+2+1」のような3つの数の足し算も取り入れます。
【注意】先取りしすぎない大切さ
年中で足し算ができる子に対しても、年齢相応の発達を意識することが大切です。
遊びの中での学びを基本とし、勉強色の強い取り組みは避けていました。
子どもの興味と発達段階のバランスを取りながら、「もっと知りたい!」という気持ちを大切に育てることが重要です。
年中さんの足し算学習におすすめの教材「こどもちゃれんじ」について
ご家庭で年中さんの足し算学習を行う上で重要なのは、学習教材の選び方です。
家庭学習教材の選び方
年齢に適した内容・難易度 であることは最も重要です。
年中さんの発達段階に合わない難しすぎる内容では、子どもの学習意欲を損なってしまいます。
楽しく取り組める工夫 があること、継続しやすいシステム も選択の重要なポイントです。
親が負担に感じない程度の分量で、子どもが飽きずに続けられる構成になっているかを確認します。
年中さんの足し算を楽しく学べる「こどもちゃれんじ」について
「こどもちゃれんじ」ステップコースは年中さん向けで、年中さんの発達に合わせた教材設計 により、足し算の基礎となる数の概念から段階的に学べます。
足し算の基礎となる数の概念学習ができ「多い・少ない」「同じ・違う」といった比較の概念から始まり、徐々に数量の理解を深めます。
しまじろうと一緒に楽しく学習できる工夫 により、子どもにとって親しみやすいキャラクターと一緒に学ぶことで、学習への抵抗感を軽減します。
段階的に数の理解を深められるカリキュラム で、無理なくステップアップできる構成になっています。
【育児】
— ガイアさん (@Szgaia1) April 25, 2020
こどもちゃれんじ5月号
今月は数の勉強🔢ドーナツで数を数えたり、足し算の概念を教えられる👍
月々1980円で毎月おもちゃたくさん来るし、学べる👍結構オススメですよ❗
なぜか英語でドーナツ注文すると断られる…
"Three chocolate donut, please!!" "No!!"#英語#こどもちゃれんじ pic.twitter.com/dU5K3trYpt
息子が0歳10ヶ月の頃から続けている、こどもちゃれんじ。
— 最所美咲 (@bariukeuke) February 5, 2023
現在は、小学校準備のチャレンジタッチ。
算数のとあるプログラムがお気に入りで繰り返し楽しんでいます。
自然と足し算•引き算ができるようになるシステムですが、間違えても何度も解けて感謝。 pic.twitter.com/X6ZqCO7BEj
※こどもちゃれんじについて詳しい内容は別記事で紹介しています 。
[足し算を楽しく学べるこどもちゃれんじの詳細はこちら]
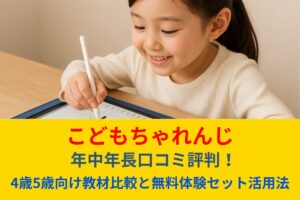
年中さん足し算できるようになる教え方 まとめ
年中さんの足し算の教え方では、子ども一人ひとりのペースを大切にすることが重要です。
同じ年齢でも発達には大きな個人差があり、それは決して能力の優劣ではありません。
・年中足し算は個人差に応じて4歳後半頃から開始してみましょう。
・年中の足し算の教え方は、具体物→指→数式の段階的アプローチが効果的。
・年中で足し算ができない場合は、できないからと比較せず個別ペースを重視し、原因を見極めた対処法が重要 。
・年中さんで足し算ができる子にも、先取りしすぎず適度な挑戦を。
・遊びの中での自然な学びを最優先に!楽しく学べる教材「こどもちゃれんじ」がおすすめ。
年中さんで足し算ができなくても、ある日突然「わかった!」と足し算ができる瞬間が必ず訪れます。
何より大切なのは、お子さんが「学ぶって楽しい」「考えるっておもしろい」と感じられることです。
一緒に楽しみながらご家庭での足し算学習に取り組みましょう。
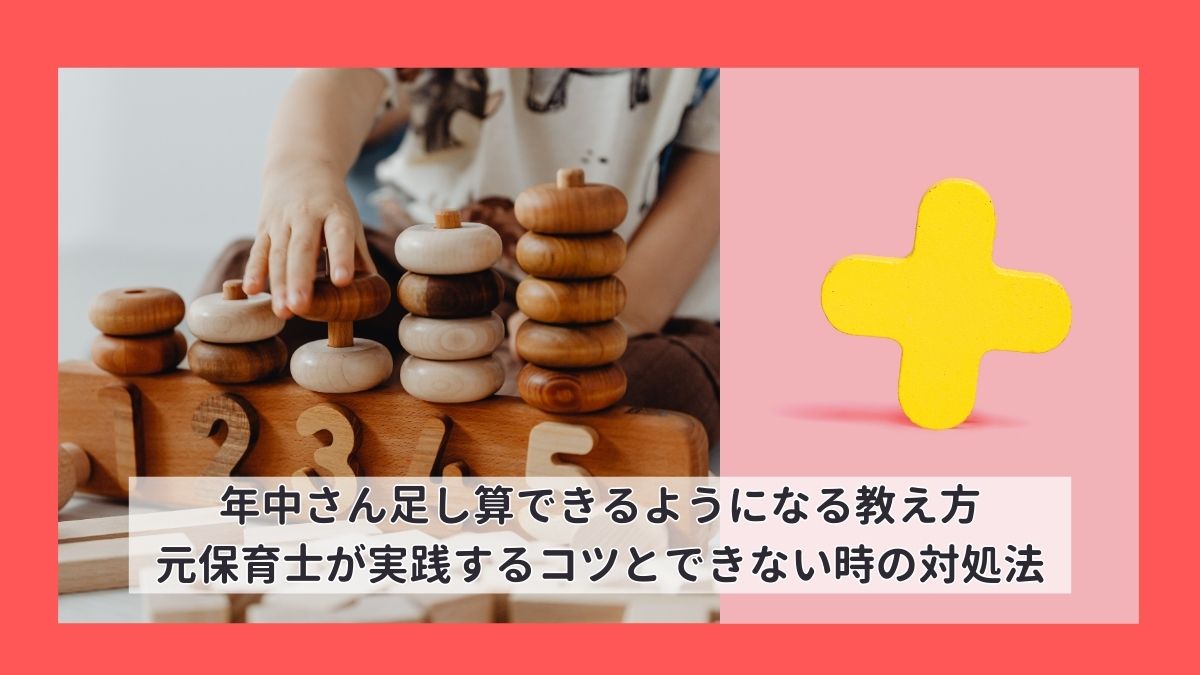


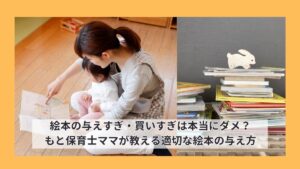




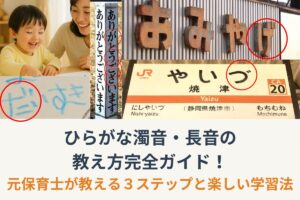
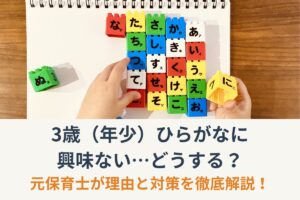
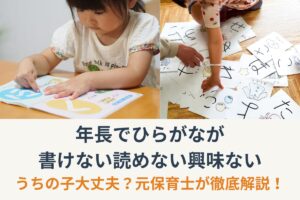
コメント