「うちの子、どうしてこんなに“勉強を教えてもらう”のが苦手なんだろう…」
せっかく丁寧に教えても、「もういい!」「わからない!」と怒り出してしまう。
他の人に教わっても素直に聞けず、親としてどう関わればいいのか分からなくなる——。
実はその“拒否反応”の裏には、単なるやる気不足ではなく、**「教わること=怖い」「できない自分を見せたくない」**という心理が隠れています。
しかし、ほんの少し関わり方を変えるだけで、子どもは驚くほど前向きに“教わる時間”を受け入れられるようになります。
💡この記事を読めば分かること
- 子どもが「勉強を教えてもらうのが苦手」になる本当の理由
- 親ができる“安心の土台づくり”と声かけのコツ
- 教わるのが苦手な子でも前向きに学べる環境の整え方
- 「わからない」を言える空気を作るための具体的な工夫
- 子どもが“教わる力”を自分で育てていく6つのステップ
この記事では、「我が子が勉強を教えてもらうのが苦手」という悩みを、親と子が一緒に克服していくための現実的な方法をお伝えします。
「教わることが怖い」子が、「教わるって楽しい」に変わるきっかけを、一緒に見つけていきましょう。
「うちの子、勉強を教えてもらうのが苦手…」と感じたら
まずは、「どうしてそうなるのか」を冷静に見つめてみましょう。
勉強を教わることへの抵抗には、子どもなりの理由や心のサインが隠れています。
勉強を教えてもらうのが苦手な子に共通する3つのサイン
「勉強を教えてもらうのが苦手で、親が教えると喧嘩になる」「他人に教わるのも嫌がる」——そんな悩みを持つ親は多いものです。
次のようなサインが見られたら、子どもは“教わること”そのものにストレスを感じている可能性があります。
・説明を聞いてもすぐに投げ出す
・質問されると固まる、泣く、黙り込む
・「もういい」「どうせわからない」と諦めてしまう
これらは「やる気がない」わけではなく、「置いていかれる不安」や「できない自分を見せたくない気持ち」が背景にあります。
つまり、“勉強が苦手”というより、教わる場面での心理的負担が大きいのです。
まず親が理解しておきたい“苦手の正体”
教わるのが苦手な子は、決して理解力が低いわけではありません。
むしろ、「説明が速い」「質問しにくい雰囲気」「過去の失敗体験」などが重なり、教えてもらう=怖い・恥ずかしいという感情が強くなっているケースが多いのです。
過去に「質問して怒られた」「理解できずに焦った」経験が積み重なると、「どうせ無理」と学ぶ前に心が閉じてしまいます。
この状態を放置すると、教わる場を避けるようになり、結果的に学ぶ機会そのものを失ってしまうことも。
子どもが“教わること”に前向きになれるようにするには、親が環境と関わり方を整えることが第一歩です。
「苦手な子」ではなく、「安心できる場がまだ見つかっていない子」と捉えることが、克服へのスタートラインになります。
勉強が苦手な子が「勉強を教えてもらうのがしんどい」と感じる理由
子どもが「教えてもらうのが苦手」と感じるのは、単なる“やる気の問題”ではありません。
そこには、ペース・雰囲気・心理的な不安という3つの壁があります。
① ペースが合わず、焦ってしまう
説明が速すぎると、子どもは「置いていかれるかも」という不安を感じます。
特に、じっくり考えるタイプの子ほどテンポが合わないと頭が真っ白になり、理解が追いつかないまま焦ってしまいます。
こんなとき、子どもは心の中でこう感じています。
- 「何を考えればいいのか分からない」
- 「次へ進むのが怖い」
- 「もう自分には無理かも…」
さらに、親から「早くやって」「次いくよ」と言われると、焦りやプレッシャーが強まり、学ぶ意欲がしぼんでしまいます。
つまり“理解力がない”のではなく、ペースが合っていないことがしんどさの原因なのです。
② 分からないと言いにくい雰囲気がある
多くの子が「分からない」と言いづらい雰囲気の中で苦しんでいます。
たとえば、
- 「また分からないの?」と責められた経験がある
- 周りができているのを見て“自分だけできない”と感じる
- 恥ずかしさやプライドが邪魔して、黙ってしまう
こうした環境では、子どもは次第に「どうせ分からない」「言っても無駄」とあきらめモードに入ります。
質問ができないまま教わると、理解が進まず、ますます“教えてもらうのが嫌”になります。
親としては、次のような雰囲気づくりが大切です。
- 「分からないって言えるのはすごいことだよ」と声をかける
- 答えよりも“考え方を話す”練習を一緒にする
- 間違いを叱らず、「ここで気づけてよかったね」と受け止める
安心して質問できる場があるだけで、子どもの表情はぐっと柔らかくなります。
③ 「教わる=できない自分を見せる」恐怖
教わる場面では、自分の弱点を見せることになります。
それが、子どもにとって何よりも怖いのです。
- 「できないと思われたくない」
- 「恥ずかしい」
- 「頑張っても無理だと思われそう」
この“見られる恐怖”が強いと、子どもは黙り込み、避け、投げ出してしまいます。
実はこれは学力の問題ではなく、自己肯定感の低下が関係しています。
「勉強を教えてもらう=自分の価値が下がる」と思ってしまうのです。
そんなときは、まず親が「できないのは恥ずかしいことじゃない」と伝えてあげることが何より大切。
“できない”を一緒に受け止める関係が、子どもの心を少しずつ開いていきます。
教わるのが苦手な子には、
- ペースを合わせること
- 安心して質問できる雰囲気を作ること
- 失敗しても大丈夫だと伝えること
この3つが、いちばんの処方箋です。
「勉強を教えてもらうのが苦手」という壁も、安心できる場と理解される体験によって、少しずつ乗り越えていけます。
勉強を 教えてもらうのが苦手な子への“寄り添いと導き”完全ガイド
「勉強を教えてもらうのが苦手で、教えるとすぐ喧嘩になる」
「他の人に教わっても素直に聞けない」
──そんな悩みを抱える親に向けて、子どもが“教わる力”を取り戻すためのサポート法を6つのステップで紹介します。
ステップ1 — 「できた」を増やして安心の土台をつくる
勉強が苦手な子は「できない経験」が多く、自信を失っています。
まずは小さな成功体験を積ませ、「教わる=怖くない」と感じさせることが大切です。
- 「今日はここまでできたね」と具体的に褒める
- 小さな目標を立て、達成したら見える形で記録する
“できた”を積み重ねることで、子どもの表情に安心と前向きさが戻ります
ステップ2 — 教える時間を短く区切って“失敗しない場”にする
長時間の勉強は苦手な子にとって負担です。
10〜15分ごとに区切り、「ここまで頑張れたね」で終える習慣をつくりましょう。
短い成功サイクルを重ねることで、子どもは「やればできる」という感覚を取り戻せます。
ステップ3 — 「わからない」と言える雰囲気を整える
教わるのが苦手な子は、“できない自分を見せる怖さ”を抱えています。
- 「どこが分からない?」ではなく「どこまで分かった?」と聞く
- 「わからなくてもいいよ」と受け止める
- 言葉に詰まったときは親が代弁して助ける
安心して話せる雰囲気が、教わる力を伸ばす第一歩です。
ステップ4 — 五感を使って理解を助ける
耳で聞くだけでは理解が難しい子も多いです。
親が“見て・動かして・話して”学べる環境を整えてあげましょう。
- 色分けノートや図で“目から理解”する
- 声に出して説明してもらい、“耳で整理”する
- 手を動かしながら考えることで“体で覚える”
学びのスタイルを合わせるだけで、「分かる!」体験が増えていきます。
ステップ5 — 相性の合う教え方・人を一緒に探す
合わない教え方では、どんな努力も実りません。
子どもが「この人なら聞ける」と感じられる環境を一緒に探しましょう。
- 動画授業で自分のペースで学ぶ
- 個別指導・家庭教師など質問しやすい環境を選ぶ
- 「この説明分かりやすいね」と共感を共有する
教わる相手との相性が合うと、子どもの吸収力は一気に上がります。
ステップ6 — “できた体験”を一緒に振り返る
学んだあとに「できたこと」を一緒に言葉にすることで、学びが定着します。
- 「今日はここができたね」と成果を言葉にする
- 「次はこれをやってみよう」と小さな見通しを立てる
この“振り返りの時間”が、次の挑戦へのエネルギーになります。
📝 まとめ:勉強を教えてもらうのが苦手な子への寄り添い方
「勉強を教えてもらうのが苦手」な子は、理解力ではなく“心の不安”に原因があることが多いです。
失敗体験の積み重ねで「できない自分を見せるのが怖い」と感じているため、まずは安心して学べる環境づくりが大切です。
🔹 親が意識したいポイント
- ① 「できた」を積み重ねて自信を回復させる
小さな成功体験を褒めて、「教わるのは怖くない」と感じさせる。 - ② 教える時間は短く、成功で終える
10〜15分で区切り、「ここまでできたね」で終えると勉強が続きやすい。 - ③ 「わからない」と言える雰囲気をつくる
「どこまで分かった?」と聞き、詰まったら親が代弁して安心させる。 - ④ 五感を使った学びで理解をサポート
図や色分け、声に出す学習などで、「わかる感覚」を増やす。 - ⑤ 相性の合う先生や教材を一緒に探す
子どもが「この人なら聞ける」と思える環境を整える。 - ⑥ 振り返りで“できた”を言葉にする
「今日はここができたね」と一緒に確認し、次への意欲を育てる。
親が“正しく教える”ことよりも、安心して挑戦できる場をつくることが何より大切です。
焦らず、「できた」「言えた」「続けられた」を一歩ずつ積み重ねていけば、
子どもは必ず「教えてもらう=成長できる時間」と感じられるようになります。




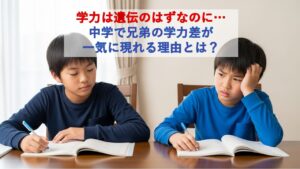

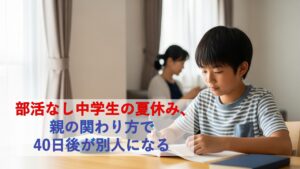
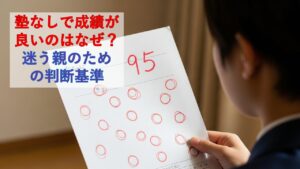

コメント