当記事はアフィリエイト広告を利用しています
「こどもちゃれんじって実際どうなの?」
「4歳や5歳から始めても効果はある?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
お子さんの成長は待ってくれません。
でも、数ある幼児教材の中から「本当に我が子に合うもの」を選ぶのは簡単ではありませんよね。
この記事を読むと、次の疑問が解決できます。
- こどもちゃれんじの年中・年長での実際の口コミや評判は?
- Z会やスマイルゼミと比較してどんなメリット・デメリットがある?
- 紙教材とタブレット、うちの子にはどちらが向いている?
- 無料体験セットの効果的な活用方法と注意点は?
- 年中・年長それぞれの年齢別おすすめポイントは?
実際の利用者の口コミや評判をもとに、こどもちゃれんじの年中・年長コースの「リアルな実態」をお伝えします。
4歳・5歳・6歳のお子さんの「学びたい気持ち」を大切に育てる第一歩として、ぜひ参考にしてください。
こどもちゃれんじ年中年長のリアルな口コミ評判
こどもちゃれんじの年中・年長コースを実際に利用している4歳・5歳・6歳の保護者たちは、どんな感想を抱いているのでしょうか?
教材の継続利用や満足度に大きく関わる「リアルな口コミ」から見えてくる傾向を見ていきましょう。
こどもちゃれんじ年中コース(4歳・5歳)口コミ傾向
年中(4歳・5歳)の子ども向け「こどもちゃれんじ すてっぷ」では、次のようなポジティブな口コミが多く見られます。
- 「毎月の教材を楽しみにしている」
- 「遊び感覚で取り組めている」
- 「自分から学ぶ姿勢が身についてきた」
教材内容は、ワークブック・知育玩具・映像教材(DVDやアプリ)などがバランスよく連携しており、子どもが飽きにくいのが特徴です。
また、以下のような保護者の声も多く見られます。
- 「仕事が忙しくても子どもが自分で進めてくれるから助かる」
- 「視力への配慮から紙教材を選んだ」
- 「机に向かう習慣が自然と身についた」
Benesseこどもちゃれんじ すてっぷ工作の動画を監督しております✂️
— 鈴木友唯 | スズキユイ (@yuidentity) April 25, 2025
出演は木下ゆーきさん、ノリから生まれたカッパのノリコもデザインさせていただき、声はまいあんつさんです!お二人とこどもたちのやりとりにクスッとさせていただきながら楽しく作らせていただきました!つくってみてね✨ pic.twitter.com/D3XIux3O5W
こどもちゃれんじ年長コース(5歳・6歳)口コミ傾向
年長(5歳・6歳)向け「こどもちゃれんじ じゃんぷ」では、小学校入学を見据えたカリキュラムが評価されています。代表的な口コミは以下の通りです。
- 「ひらがな・カタカナの読み書きができるようになった」
- 「時計や数の概念も理解できた」
- 「小学校の勉強への不安が減った」
一方で、次のようなややネガティブな声も見られます。
- 「簡単すぎてすぐに終わってしまう」
- 「もっと応用問題がほしい」
このため、Z会やスマイルゼミなど、より発展的な教材との比較を始めるご家庭も少なくありません。
それでも、「子どもが1人で進められる」「自信につながる設計」は高く評価されています。
こどもちゃれんじの「とけいマスター」
— やっしょ (@SY8189118er) April 8, 2024
時計の読み方を覚えられるのはもちろん、「てきぱきタイマー」がめちゃくちゃ便利
1〜5分でセットできて楽しい音楽が流れる
残り時間が目に見えて分かりやすいので子供も「早くしなきゃ!」とゲーム感覚で楽しみながら朝の支度ややる事が出来る pic.twitter.com/Tc5PbRXgk6
こどもちゃれんじと他社教材との比較
こどもちゃれんじ以外にも、Z会やスマイルゼミ、公文といった幼児向けの教材は多く存在します。
ここでは、それぞれの教材が持つ特徴や違いを比較しながら、どんな家庭に向いているかを見ていきましょう。
料金とコストパフォーマンス
「こどもちゃれんじ」は、他の人気教材と比較しても、コストパフォーマンスが非常に高いと評価されています。
月額1,000~2,000円台から始められるため、家計にやさしく、継続しやすいのが最大の特徴です。
一方で、Z会やスマイルゼミは料金は高くなりがちです。
- こどもちゃれんじ(タブレット&実物教材):月額 約2,730円〜(税込)
- こどもちゃれんじ(タブレットのみ):月額 約1,980円〜(税込)
- スマイルゼミ:月額 約3,630円〜(税込)(専用タブレット代別)
- Z会幼児コース:月額 約3,383円〜(税込)(紙教材+添削)
また、こどもちゃれんじでは「タブレットのみ」(デジタルスタイル)と「タブレット&実物教材」(ハイブリッドスタイル)の選択制があるため、家庭のニーズに合わせて柔軟に対応可能です。
学習内容・子どもの自走力
Z会や公文は、「学力の定着」や「発展学習」に強みがある反面、親の関与が必須となる傾向があります。
一方で、こどもちゃれんじは「自分で考える力」や「習慣づけ」に重点を置いており、紙・タブレットどちらの形式でも子どもが自走しやすい設計が魅力です。
スマイルゼミはタブレット操作を通じてゲーム感覚で進められる点が人気ですが、使用時間や姿勢、視力への配慮が必要です。
- こどもちゃれんじ:遊びと学びが融合。タブレット版も含め親の手がかからない設計。
- Z会:内容が高度で思考力が育つが、親のフォローが欠かせない。
- スマイルゼミ:楽しく続けられるが、デジタル慣れしすぎないよう注意が必要。
「忙しくても子どもが1人で学べる教材がいい」という方には、こどもちゃれんじの柔軟な選択肢(紙・タブレット両対応)は非常に魅力的です。
こどもちゃれんじ実物教材とタブレット、どちらが合う?
「実物とタブレットか、タブレットのみか、どちらがうちの子に向いているの?」という悩みは、多くの保護者が抱えるテーマです。
それぞれの特性と向き・不向きを知ることで、より納得感のある選択ができるようになります。
実物教材の特徴と向き・不向き
こどもちゃれんじの実物教材は、手を動かして書いたり貼ったりする体験を大切にしており、「アナログの良さ」が活かされています。
鉛筆やクレヨンを使う作業が中心で、文字や図形の書き取り・なぞり、工作などの体験型学習が可能です。
「机に向かう習慣をつけたい」「目を使いすぎるのが心配」「紙面での反復練習が得意」というご家庭に適しています。
- メリット: 視力への負担が少ない、手を使った学習で記憶に残りやすい
- デメリット: 親がある程度付き添う必要がある、教材がかさばる
こどもちゃれんじ、昨日届いた分もうおわた🐯
— ちょろ✈︎next9月ハワイ🌺🌴 (@choro__ch) March 27, 2025
ちゃれんじって9月生まれに合わせて作ってるらしく、9月生まれの息子にドンピシャなようでどのワークよりも楽しんでやってる。
他の教材をと思ったけどやっぱりちゃれんじのオプションで教材追加するかなあ。
プログラミングか普通のか🤔➿ pic.twitter.com/RBkny8jnTb
タブレット教材の利点と注意点
タブレット教材は、アニメーションや音声ナビゲーションで子どもが自力で進めやすく、親の手間が減る点が大きな利点です。
1回のレッスンが約10分程度で完結するよう設計されており、集中力が持続しにくい子どもにも向いています。
- メリット: 自走型で取り組める、視覚・聴覚に訴える設計、ゲーム感覚で楽しい
- デメリット: 視力や姿勢への配慮が必要、家庭によってはブルーライト制限の対策も必要
「自分でどんどん進めてくれると助かる」「子どもがタブレット操作に抵抗がない」家庭には、非常に向いている選択肢といえるでしょう。
こどもちゃれんじ無料体験セットを活用しよう
購入前に「お子さんとの相性」を試せるのが、こどもちゃれんじの無料体験セットの魅力です。
内容をただ試すだけでなく、子どもの反応や興味の方向性を知る手がかりとしても活用できます。
無料体験セット内容と子どもの反応
こどもちゃれんじの「無料体験セット」は、年齢や時期によって内容が異なりますが、基本的に以下のようなアイテムが含まれています。
- ミニワークブック(1〜2冊)
- 知育玩具または体験用おもちゃ
- 映像教材のDVD(もしくは動画視聴コード)
- 保護者向けガイドブック・教材カタログ
特に子どもたちに好評なのは、教材キャラクターの「しまじろう」が登場するDVDやおもちゃです。
「届いたその日に夢中で遊んでいた」「ワークを何度も繰り返していた」という声も多く、教材への反応を試すには絶好の機会です。
また、映像教材と連動するしかけや、付録で手を動かす体験により、短時間でも集中して学べることが特徴です。
無料体験セット活用のコツと注意点
無料体験セットを最大限に活かすには、いくつかのポイントがあります。
- 子どもの「反応」をよく観察する:興味のある・ない分野を見極めましょう。
- 親子で一緒に取り組む時間をつくる:はじめの印象が継続に影響します。
- ワークや付録を無理に全部やらせない:楽しさが優先です。
注意点としては、資料請求の際に「無料体験セット」が届かない時期もある点です。
申し込み画面に「体験教材あり」と明記されているか確認しましょう。
また、1世帯1回限りの申し込みとなるため、兄弟での重複請求はできない点にも注意が必要です。
総じて、無料体験セットは、教材との相性を見極めるだけでなく、子どもの学びの入り口をつくる貴重なツールとなります。
【↓ 無料体験セットを申し込む↓】
こどもちゃれんじ年中年長 やめた人の声・デメリットとは?
どんなに評価の高い教材でも、すべての子どもや家庭に合うとは限りません。
ここでは、こどもちゃれんじ年中・年長コースを「やめた」保護者の声をもとに、理由とその対策を見ていきます。
続かなかった理由と対策
こどもちゃれんじ年中・年長コースを続けられなかった家庭の理由として、以下のような声が多く見られます。
- 「教材がたまってしまい、親がプレッシャーを感じた」
- 「子どもが最初は興味を持ったが、すぐに飽きてしまった」
- 「親の付き添いが必要で、継続が難しかった」
これらの声に対しては、次のような工夫が効果的です。
- 週末に“教材タイム”を設けるなど、無理のないスケジュール管理をする
- 子どもが関心を持つ内容を把握し、教材の中から好みに合う要素を優先的に活用する
- 「実物教材+タブレット」から「タブレット教材のみ」に切り替えて、自走型のスタイルに移行する
すべてを完璧にやる必要はなく、「親子で楽しめたらOK」という意識で取り組むことが、長く続けるコツです。
他教材への乗り換え例
こどもちゃれんじからZ会やスマイルゼミへ乗り換える家庭もあります。
乗り換えの理由としては、以下のようなケースが代表的です。
- 「もっと学習の質を高めたかった」
- 「キャラクター学習よりも学力重視にシフトしたい」
- 「子どもがゲーム感覚で進めるスマイルゼミに興味を持った」
ただし、こどもちゃれんじで“学習の習慣”を先に身につけたからこそ、次のステップへスムーズに移行できたという声も多くあります。
「最初の教材」として、こどもちゃれんじは非常に価値のある選択肢だといえるでしょう。
こどもちゃれんじ年中年長おすすめポイントまとめ
こどもちゃれんじは年齢に応じたステップ設計がされており、4歳・5歳それぞれに適した教材内容が用意されています。
ここでは、それぞれの年齢に特におすすめできる理由を整理してご紹介します。
年中(4歳・5歳)のおすすめポイント
年中(4歳・5歳)向けの「こどもちゃれんじ すてっぷ」は、幼児期の「できるようになった!」を引き出す設計が魅力です。
- 「ひらがなの読み書き」や「数の概念」など、学びの入口に最適
- ワーク+知育玩具+映像教材の三位一体設計で飽きにくい
- 親が忙しくても、自走で取り組めるシーンが増える
- 「しまじろう」キャラによる信頼と安心感で、初めての学習が楽しい体験に
「学習の楽しさ」や「習慣化の土台」をつくるのにぴったりな時期といえるでしょう。
年長(5歳・6歳)のおすすめポイント
年長(5歳・6歳)向けの「こどもちゃれんじ じゃんぷ」は、小学校入学準備に特化した内容になっています。
- 「ひらがな・カタカナの書き」「時計の読み方」など実践的なスキルに強い
- 学習リズムを整えるカレンダーや生活習慣の指導も充実
- タブレット版では一人で学び進められる工夫が満載
- 「入学までに何をやっておけばいいか?」の不安を自然と解消できる
楽しく学びながら、確実にステップアップ”を実現したいご家庭に最適です。
こどもちゃれんじ年中年長コースで実現できる、家族の未来ストーリー
【ある日の夕方、リビングで起こった小さな奇跡】
5歳の娘が、いつものように「こどもちゃれんじ」のワークに取り組んでいました。
突然、娘が振り返って言いました。
「ママ、見て!『ありがとう』って書けたよ!」
小さな手で一生懸命書いた、少しゆがんだ「ありがとう」の文字。
その瞬間、胸がいっぱいになって、思わず涙がこぼれそうになりました。
「上手に書けたね。誰に『ありがとう』って伝えたいの?」
「パパとママに。いつもお仕事がんばってくれてありがとうって」
娘が書いてくれた小さな手紙を、冷蔵庫に大切に貼りました。
こどもちゃれんじを始める前は、「勉強なんて嫌い」と言っていた娘。
でも今では、毎日自分から机に向かって、楽しそうに学んでいます。
月額2,000円台の投資が、娘の人生の土台をつくってくれていました。
【あなたのお子さんにも、同じような未来が待っています】
毎日忙しい中でも、お子さんが一人で楽しく学べる環境をつくれたら。
文字が書けるようになって、家族への気持ちを伝えられるようになったら。
そんな「ちょっと先の未来」が、こどもちゃれんじで実現できるのです。
今なら無料体験セットで、お子さんの反応を確かめることができます。
あの小さな「ありがとう」の文字のように、きっとお子さんからも素敵なサプライズが届くはずです。
【↓ 無料体験セットを申し込む↓】
※資料請求は1分で完了。お子さんの成長の第一歩を、今日から始めませんか?
【期間限定キャンペーン】
<注意>対象期間は、体験セット申込日ではなく入会日です!体験セットはさらに早く申し込みましょう。
・7/31までに「ほっぷ」「すてっぷ」8月号をご入会された方限定で、専用タブレットが通常月々1,038円×24回払いのところ、実質月々997円に!




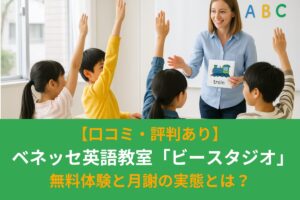

コメント